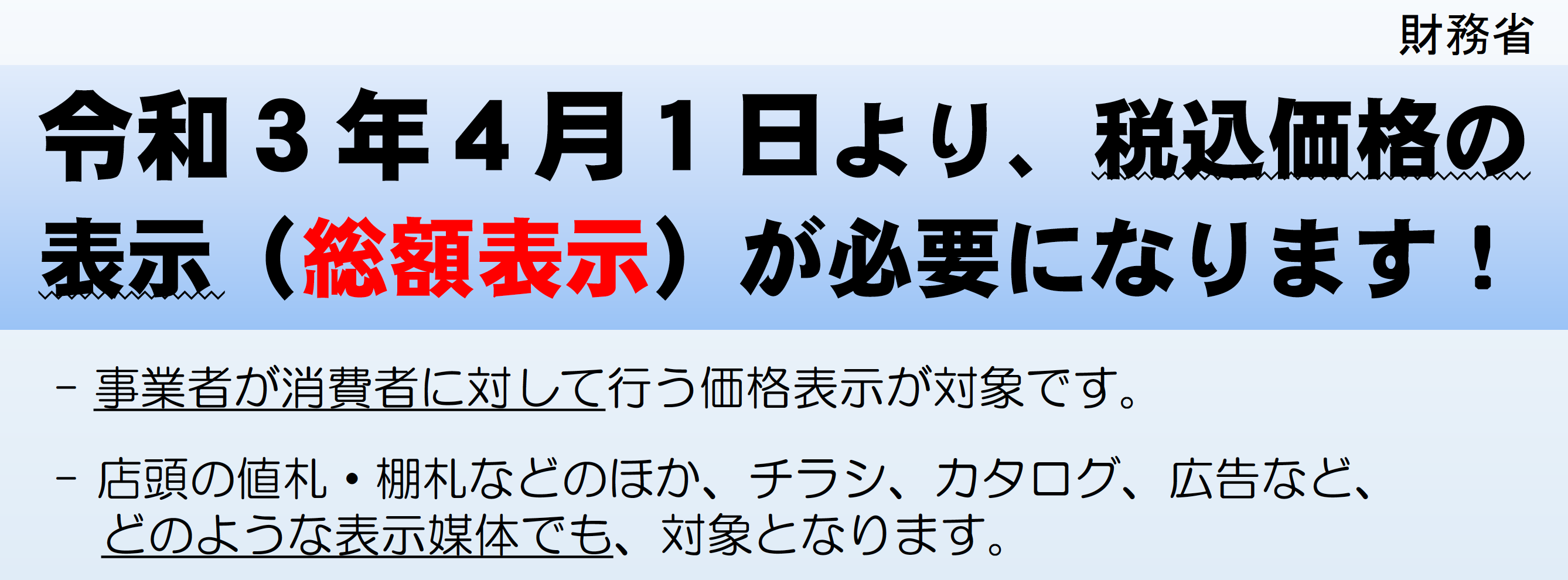料金表示がわかりにくいだけで、買い物したくなくなりますよね。
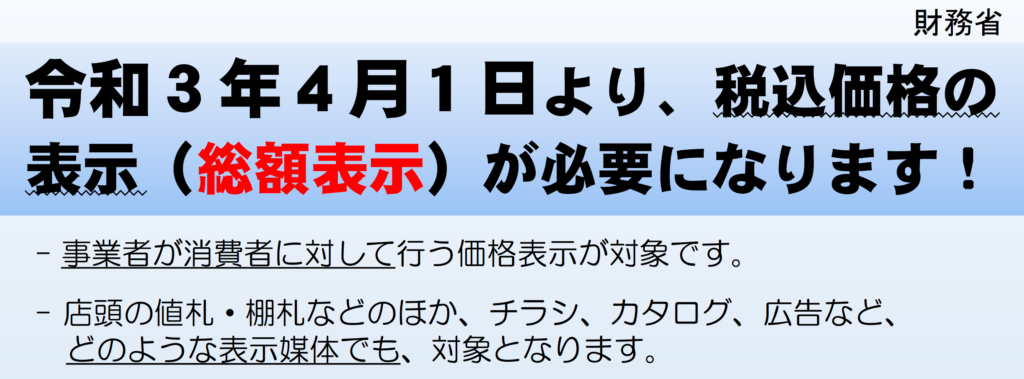
価格がわかりにくいと買い物をする気がなくなる
買い物をするときなどに、「税抜価格なのか、税込価格なのか」をあまり意識していなくて驚くことってありますよね。
たとえば、ちょっと奮発して食べた1,200円のランチを、
「税込価格だとおもって」会計をしたら、
「1,320円。あれっ、なんか思っていたよりも高いなぁ。」
となることがあったりしませんか。
「あっ、1,200円は税抜価格だったんだ。」
と気づいて納得をするのですが、何か腑に落ちない気持ちになりますよね。
また、子どものおつかいでも、
「ビーマンが150円だったら買ってきて。」
と買い物を頼んだとしても、
「145円って書いてあって、それが本当の金額かどうかわからないから買えなかった。。。」
ということもあったります(こどもだと税抜価格と税込価格に混乱をしてしまい、値段がわからなくなるようです)。
「あるお店では、税抜価格。」
「あるお店は、税込価格。」
だと混乱するのは、大人もこどもも影響はおなじですよね。
税抜価格のほうが、消費税の痛税感というものを感じ取ることができるので、あるべき姿だといわれる方も居ます。
しかし、「いちいちそんなに詳しく値札を見ない人間としては」、税込価格のほうが買い物はしやすいと感じます。
2021年4月1日からは、価格は税込価格が義務になります
価格はいくらなのかはっきり分かるほうが、買い物をするときに安心感があるものです。
そんな方に朗報です。
2021年4月1日からは、事業者(お店など)が消費者(あなた)に対して表示する値段の表記は、総額表示が義務となります。
「税込価格が、世の中のスタンダード」になります。
店頭の値札だけではなく、チラシ、カタログ広告など、どのような表示媒体でも、税込価格となります。
価格表示の例としては、財務省から以下のようなものが挙げられています。
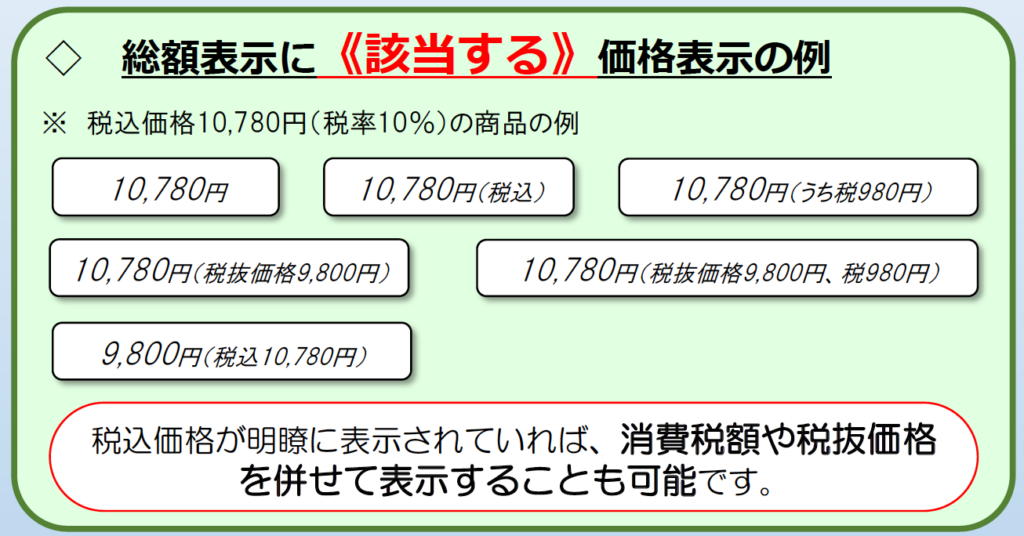
税込価格で表示するといっても、いくつかのバリエーションが認められています。
しかし、ここはもうバシッと、
ランチ 1,320円!!!
と書かれていたほうが、気持ちがいいですよね。
それが、
ランチ 1,200円(税込1,320円)
という表記だと、一瞬混乱をするので避けてほしいと思います。
いままで認められていた、下記のような税抜価格での表示は禁止となります。
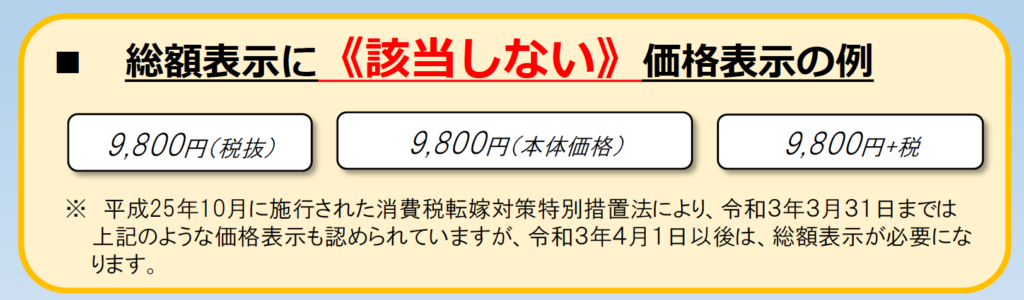
禁止といっても、特に罰則等は設けられていません。
とはいっても、「わかりやすさを重視するため」にも税込価格での表示が、世の中には求められています。
まとめ
税金を意識するためには、税抜表示のほうがいいという意見もわかります。
しかし、買い物をするときに、
「価格がわからないことは、非常に怖いことです。」
どんなに美味しそうな飲食店でも、「価格が分かりづらい。」とそのお店に入る気はなくなります。
ネットショッピングでも価格表示がわかりにくければ、
「高くてもいいから、価格がわかりやすいAmazonで買おう。」となります。
ヨーロッパのほとんどの国では、価格は総額表示(税込価格)となっているようです。
「義務だから税込価格にする。」
というよりも、
「お客様にわかりやすくするために、税込価格にする。」
というスタンスで、税込価格表示に対応していきましょう。
【おわりに】
わたしの担当だった、確定申告の無料相談会が昨今の事情で中止に。
来年からはやりたくないけど、一年生の今年は「税理士らしい」仕事の無料相談会をやりたかったので残念です。
電話相談の方も中止になったりするのかなぁ。。。
【一日一新】
ある場所のバーミアン